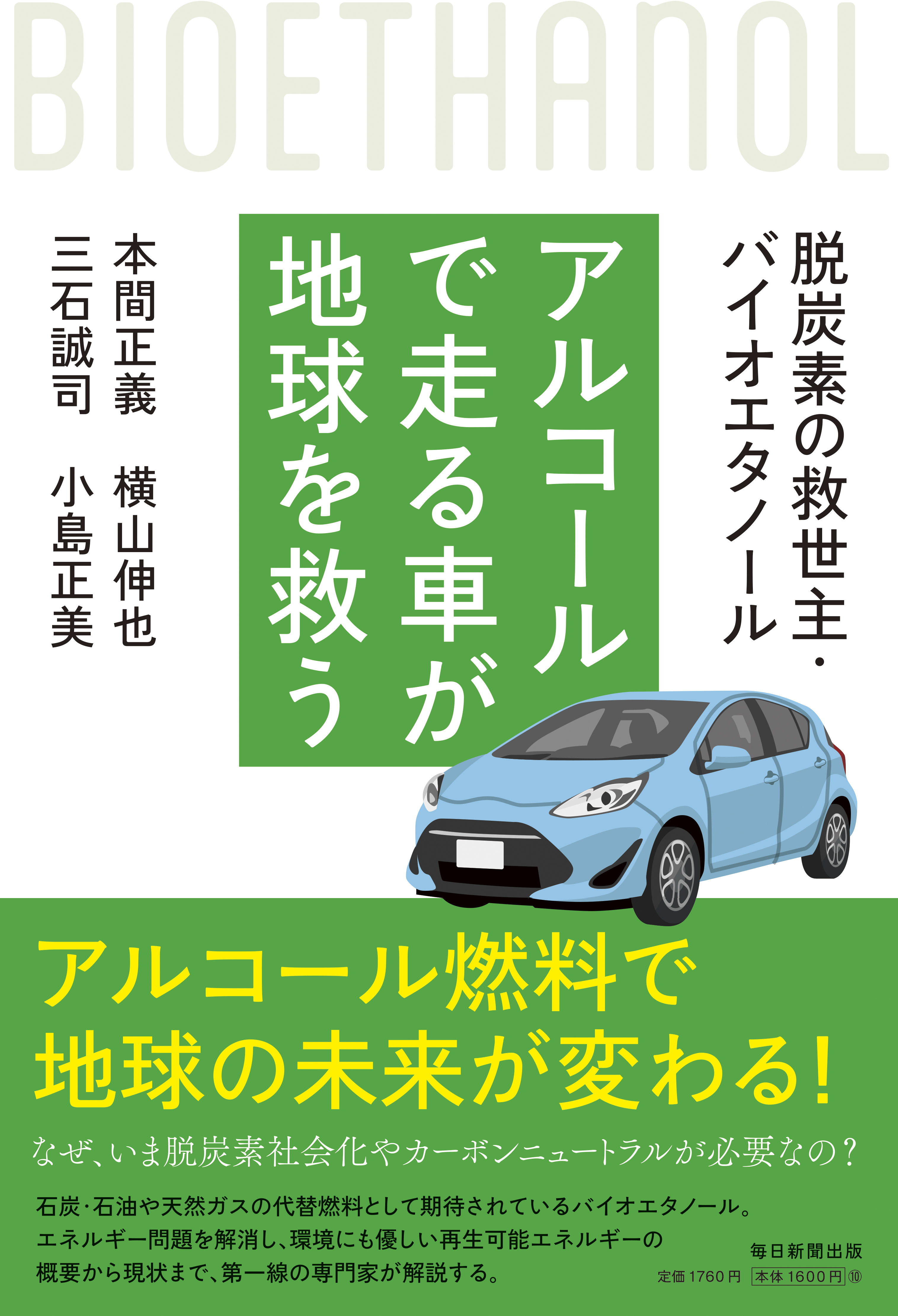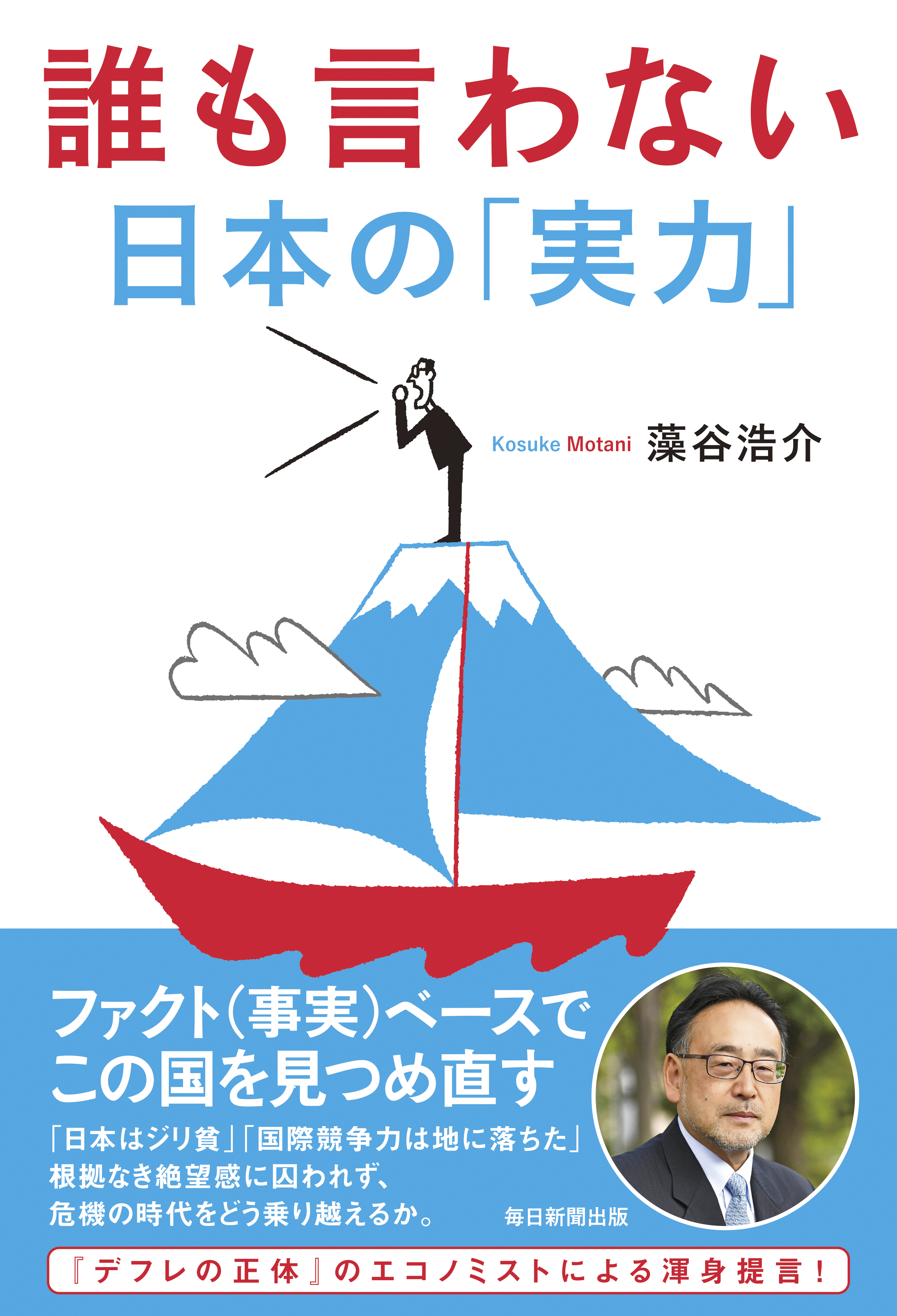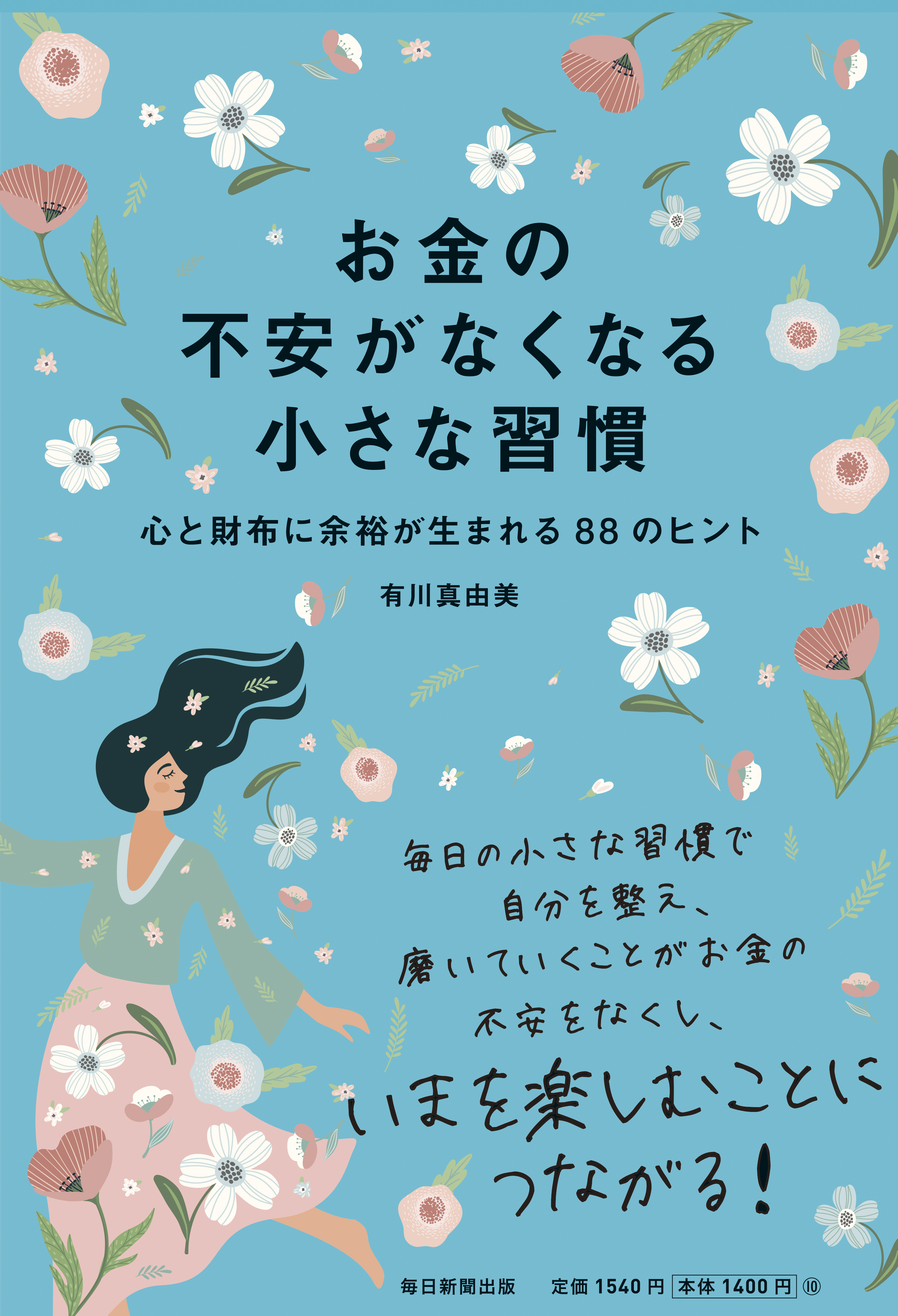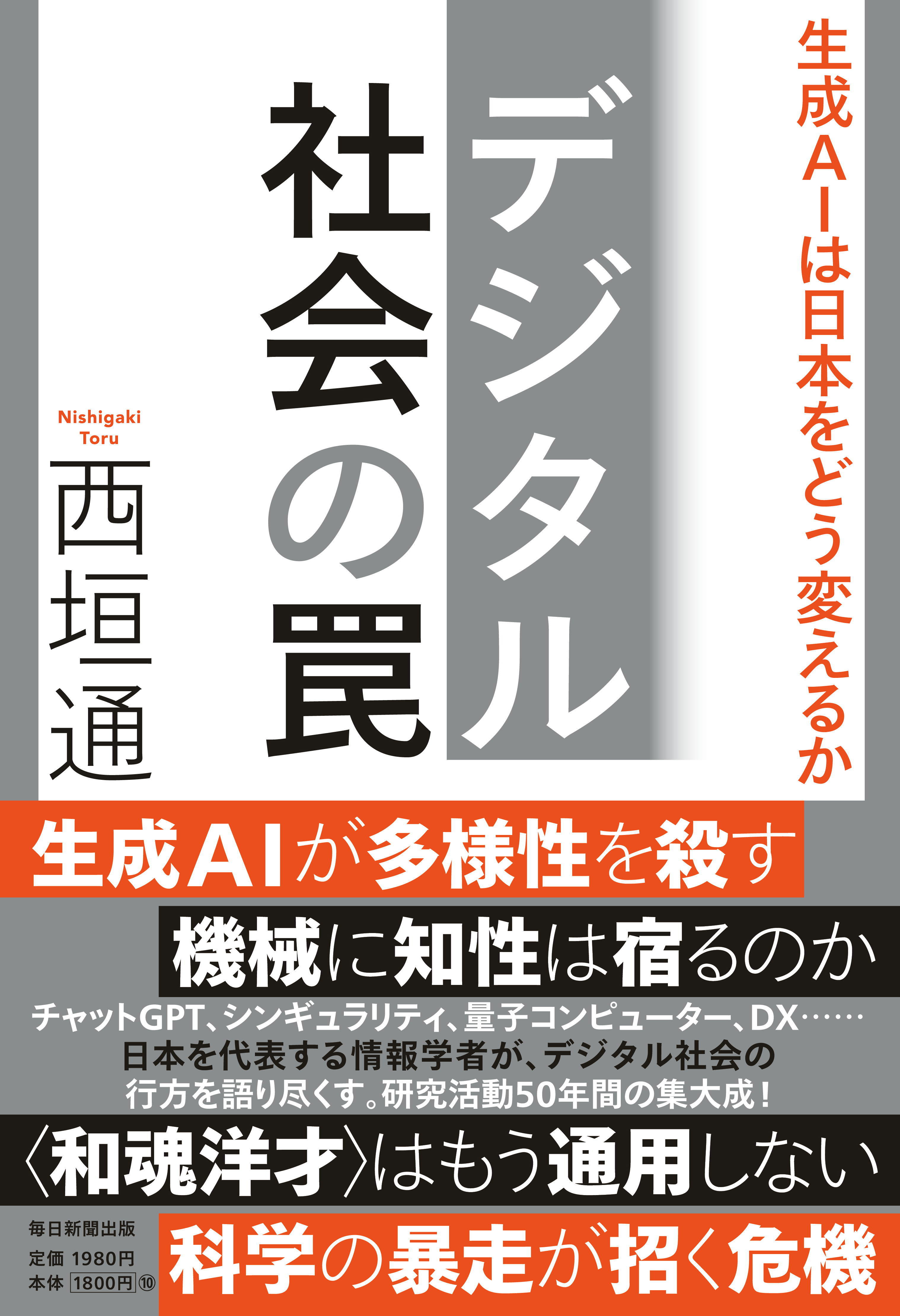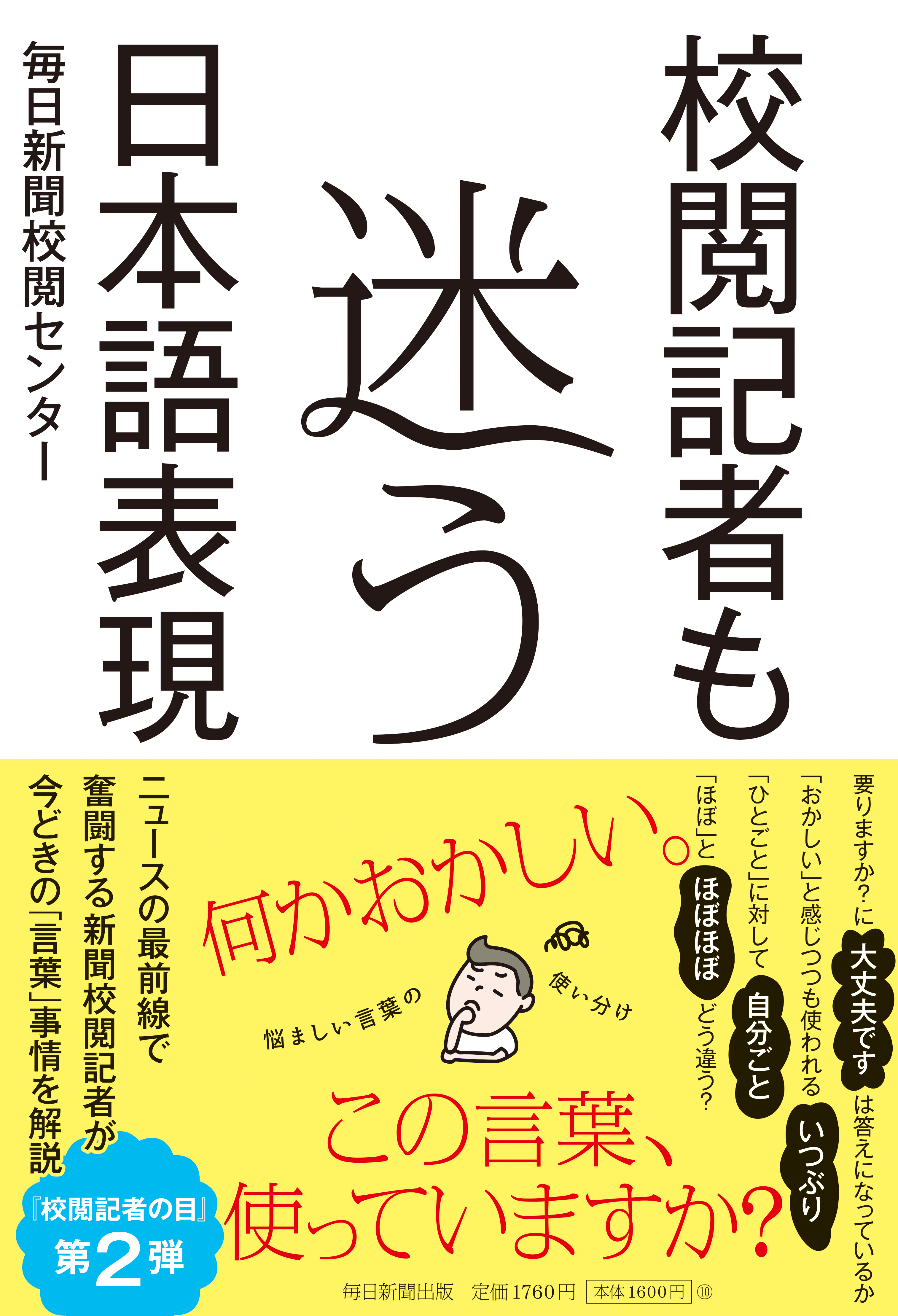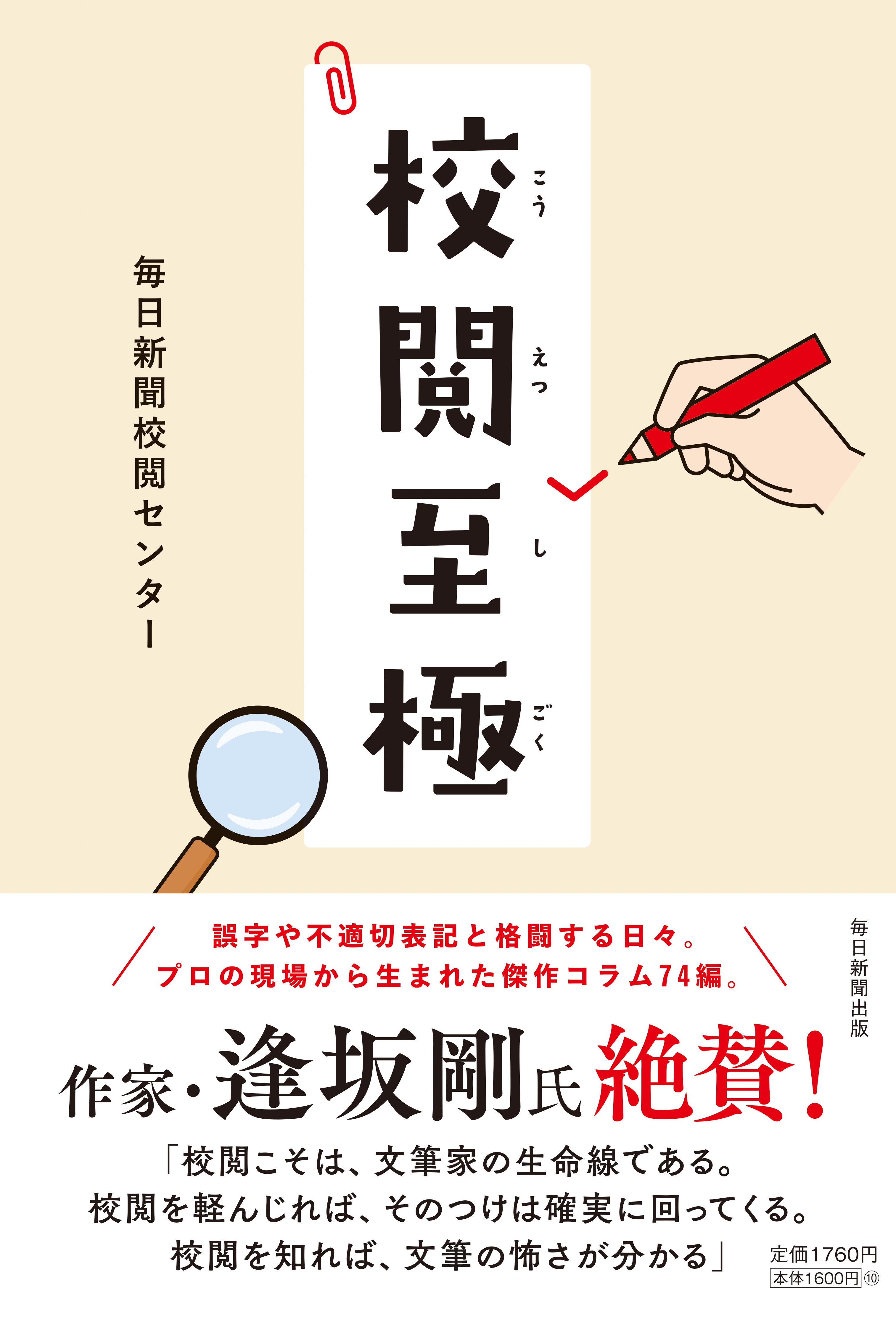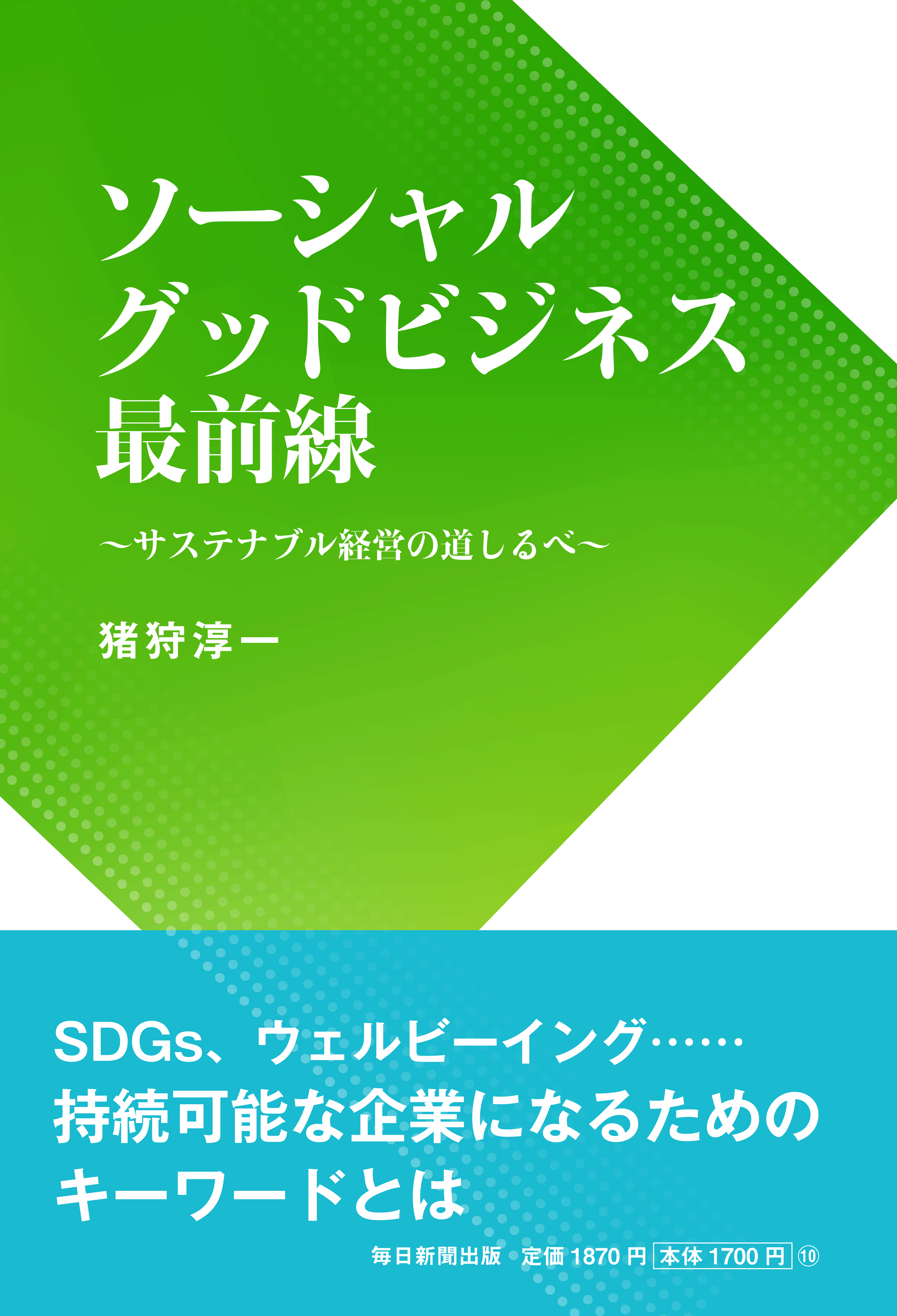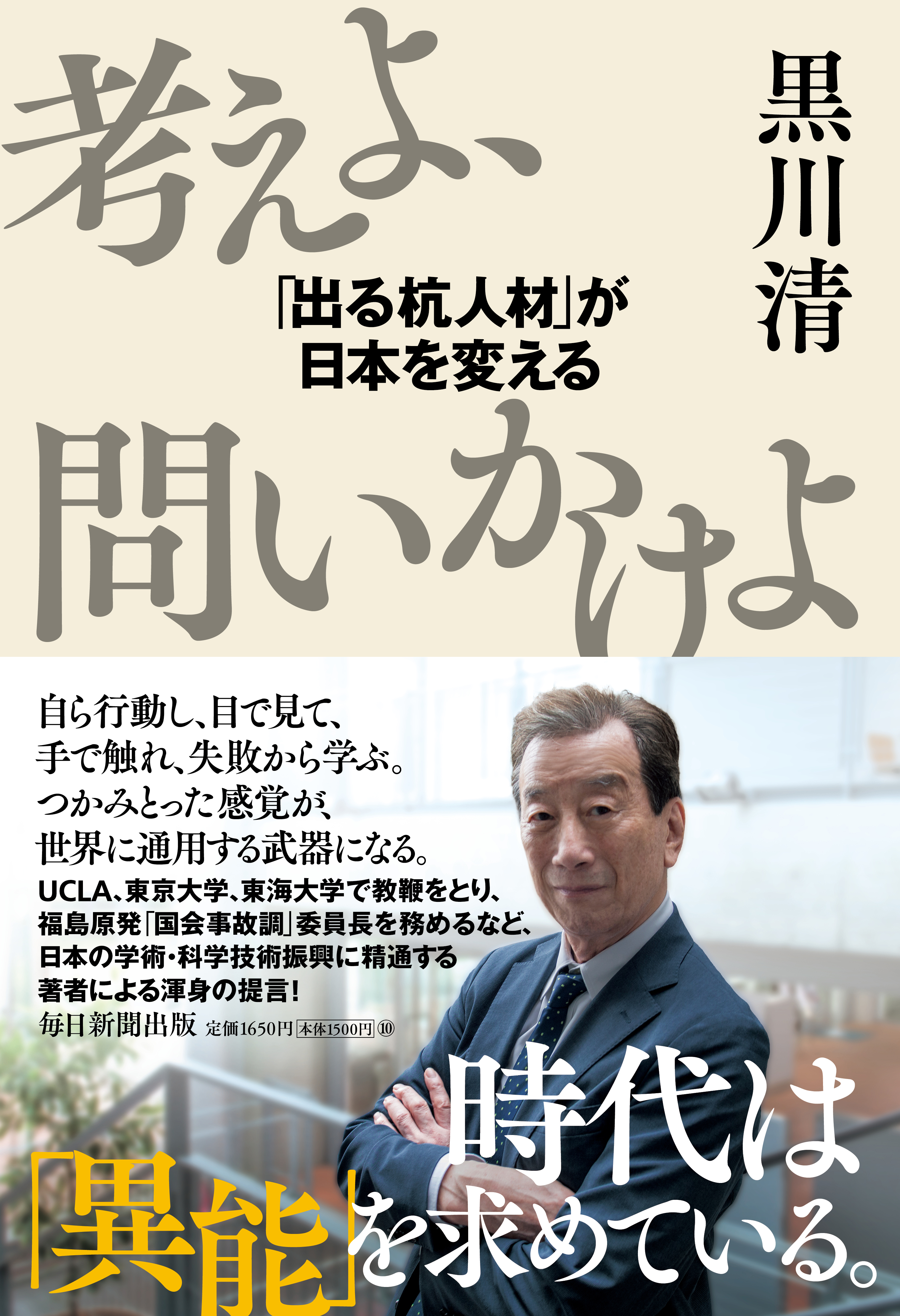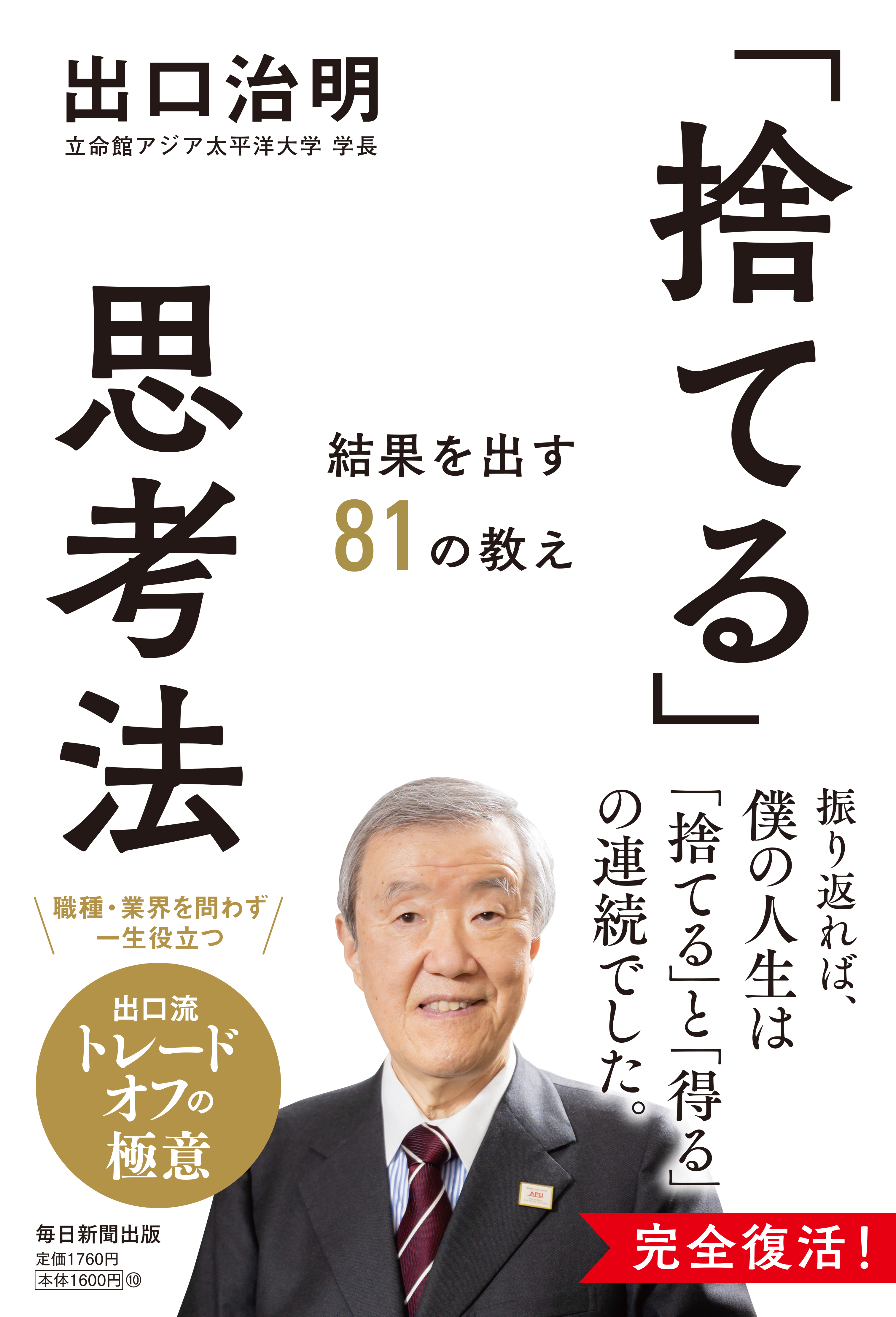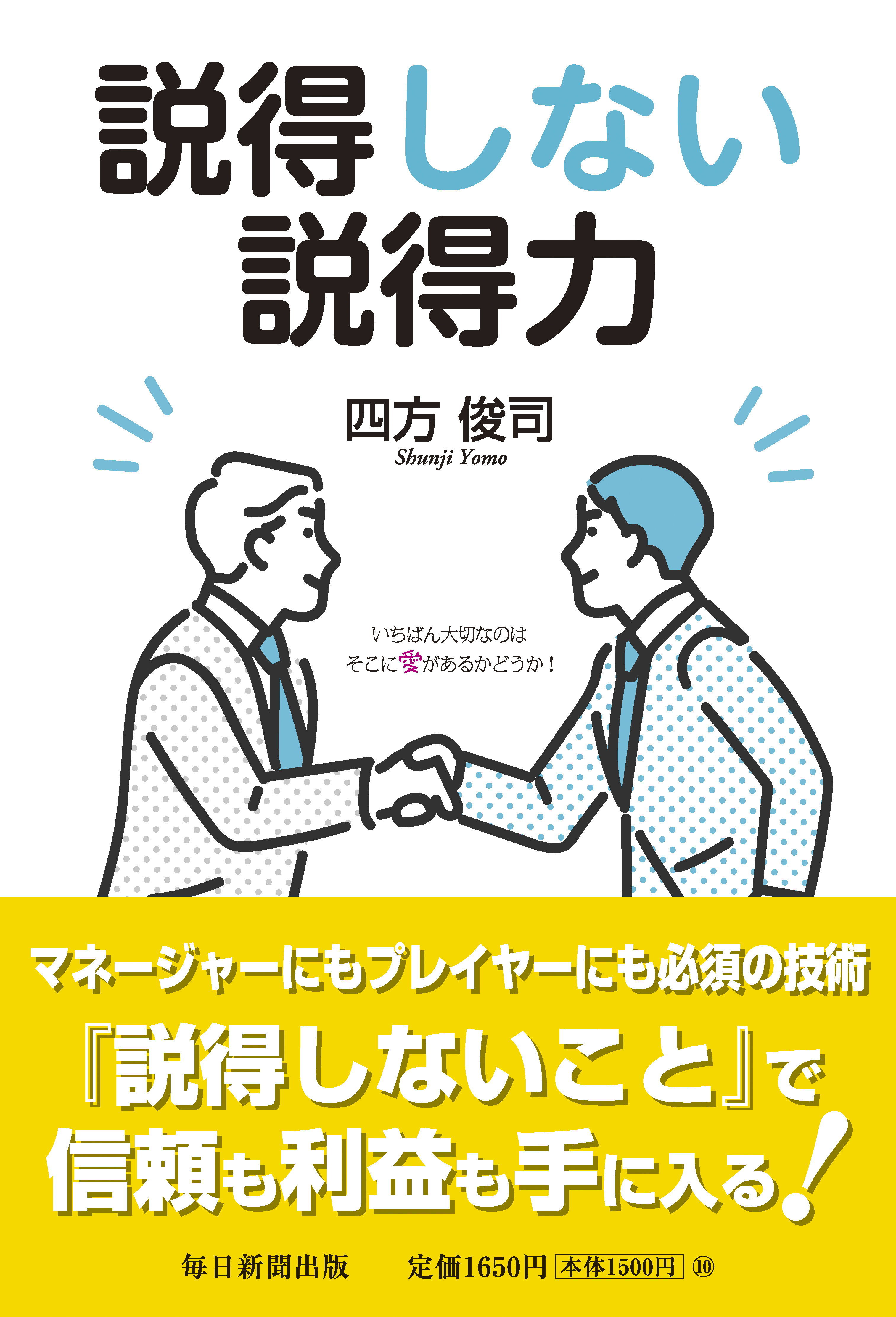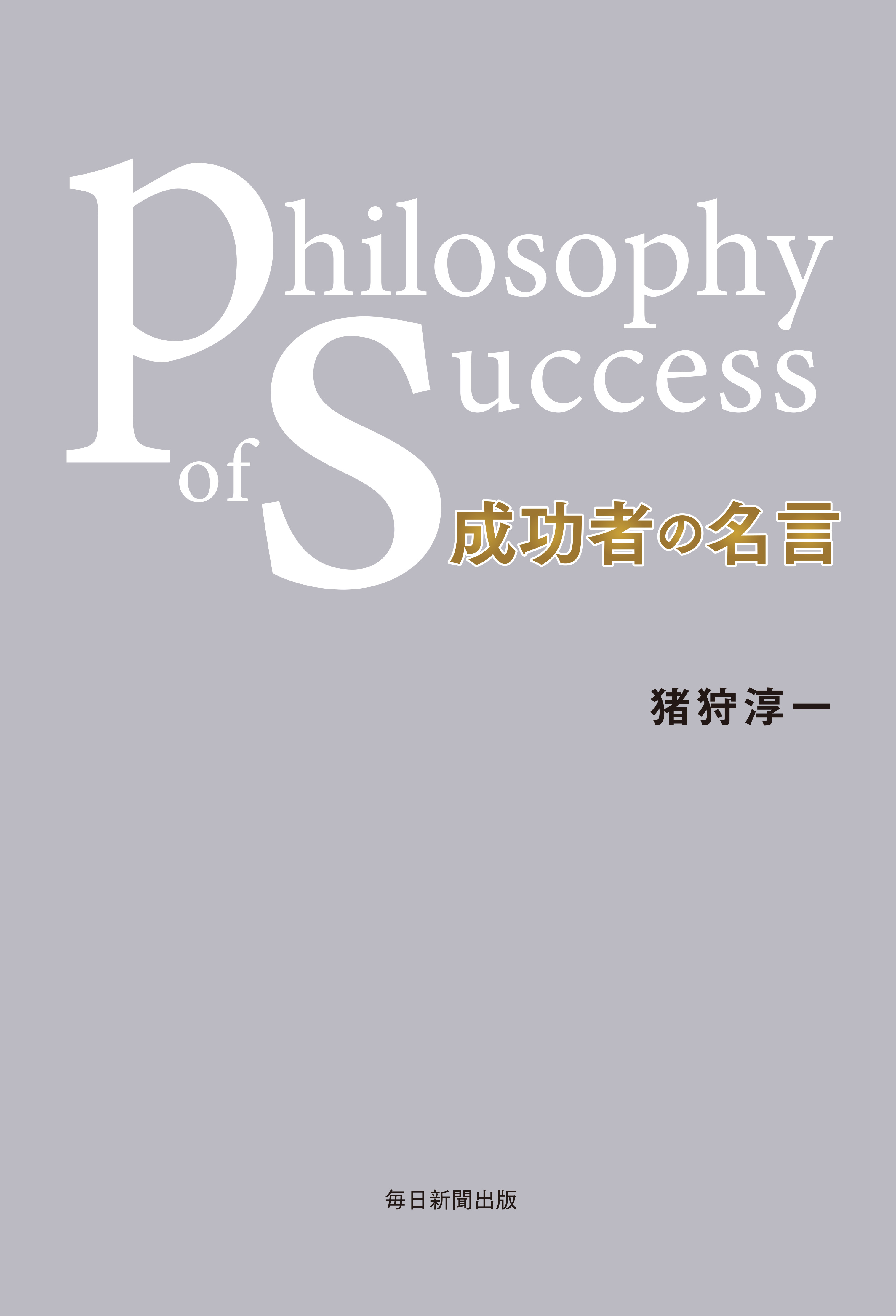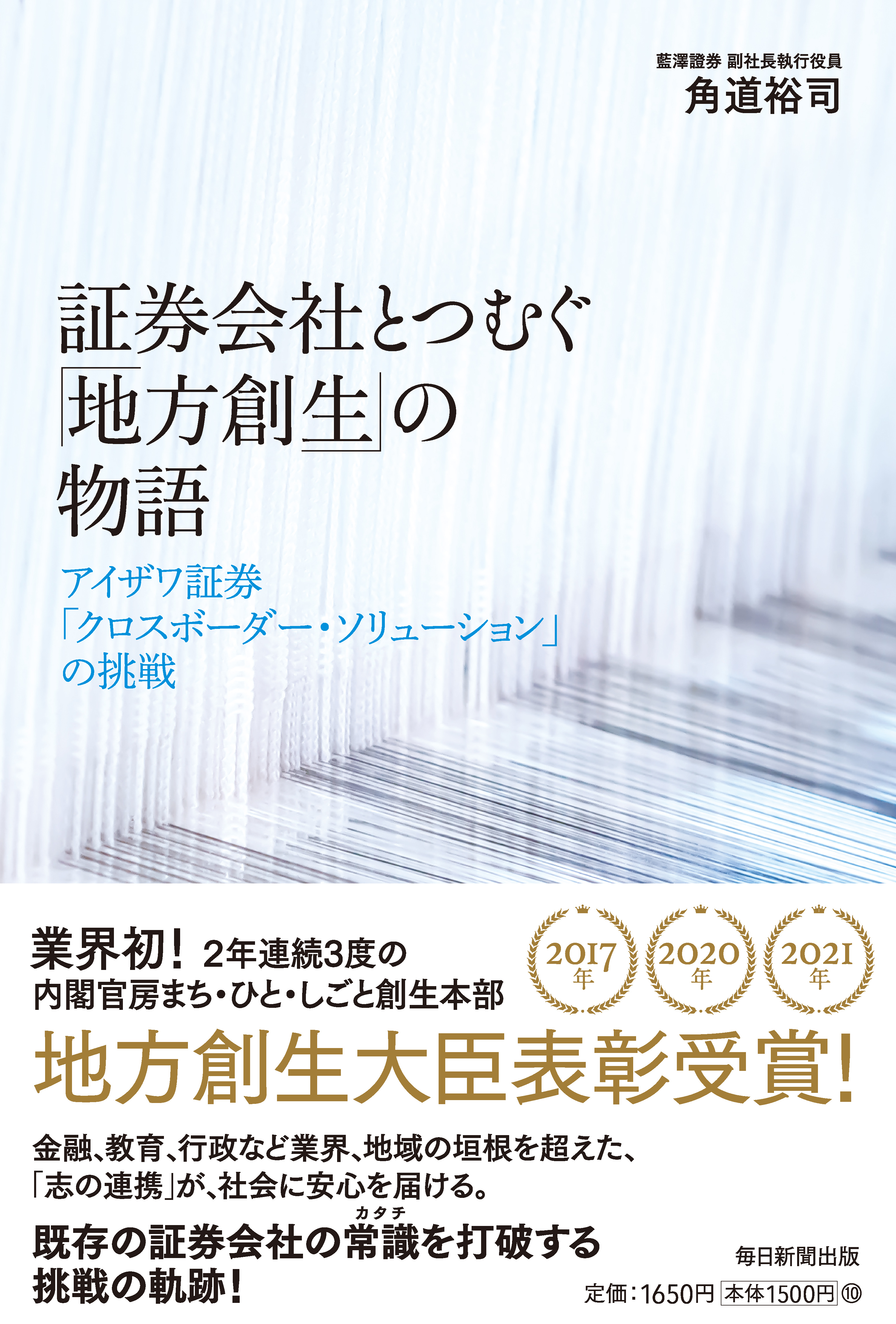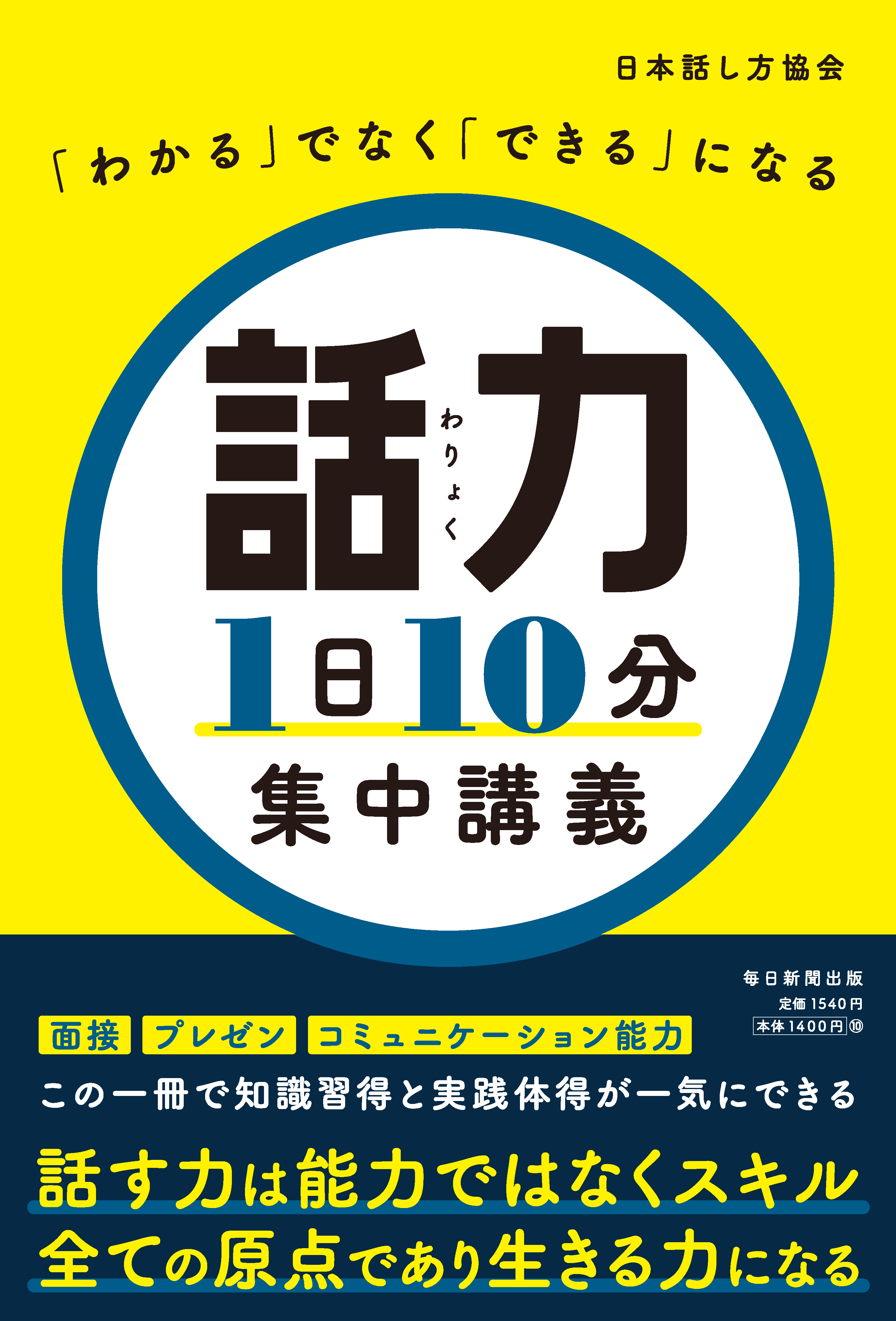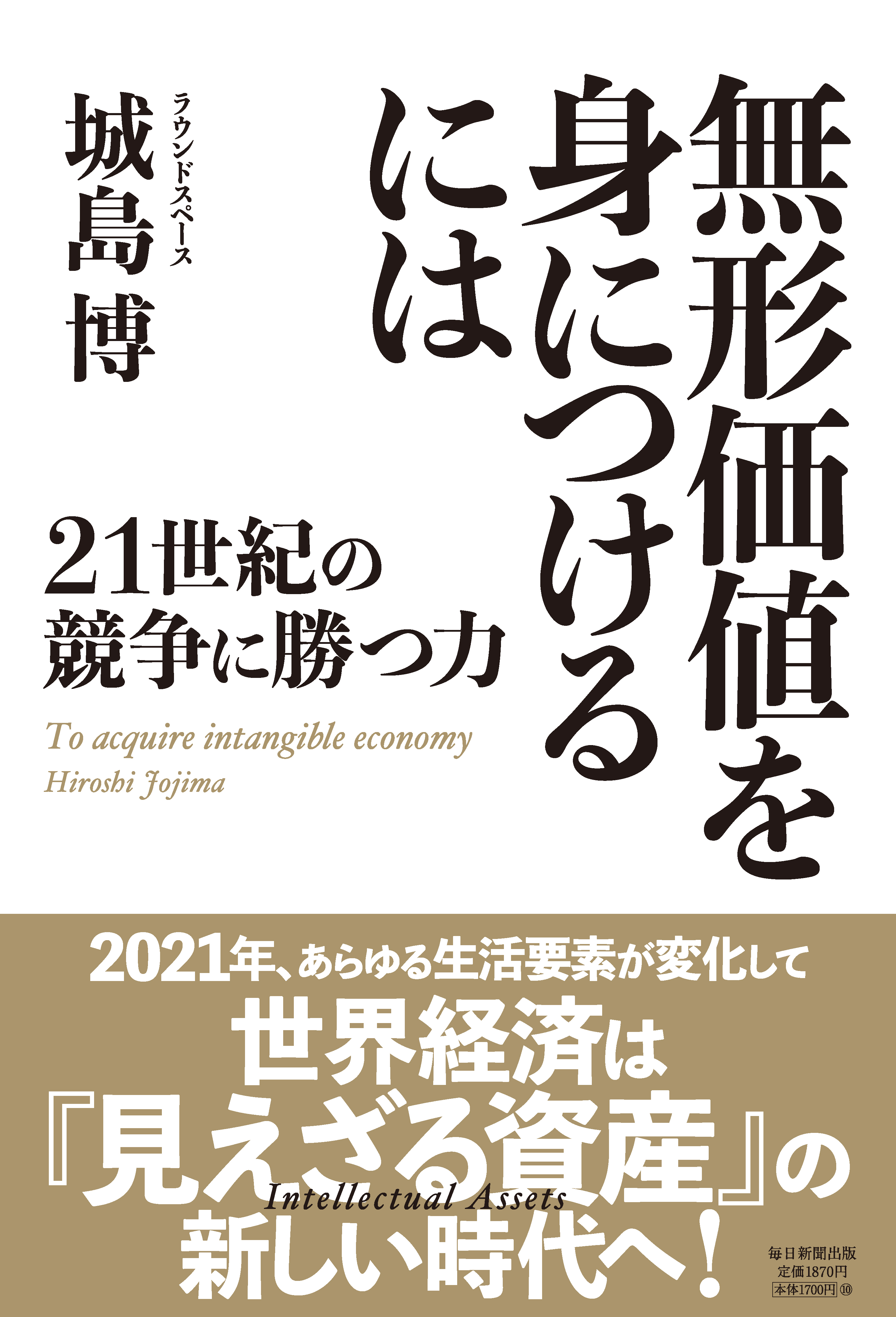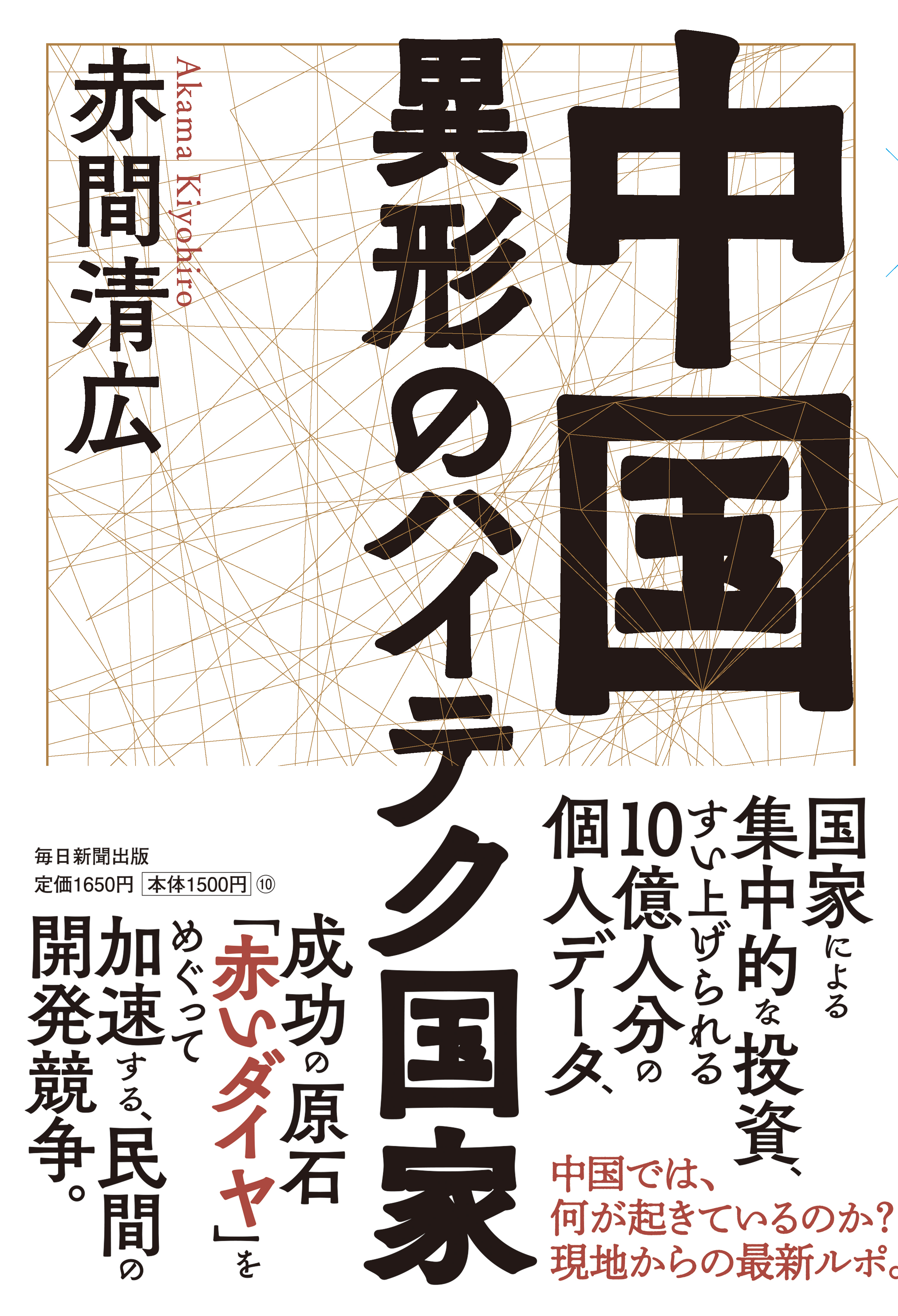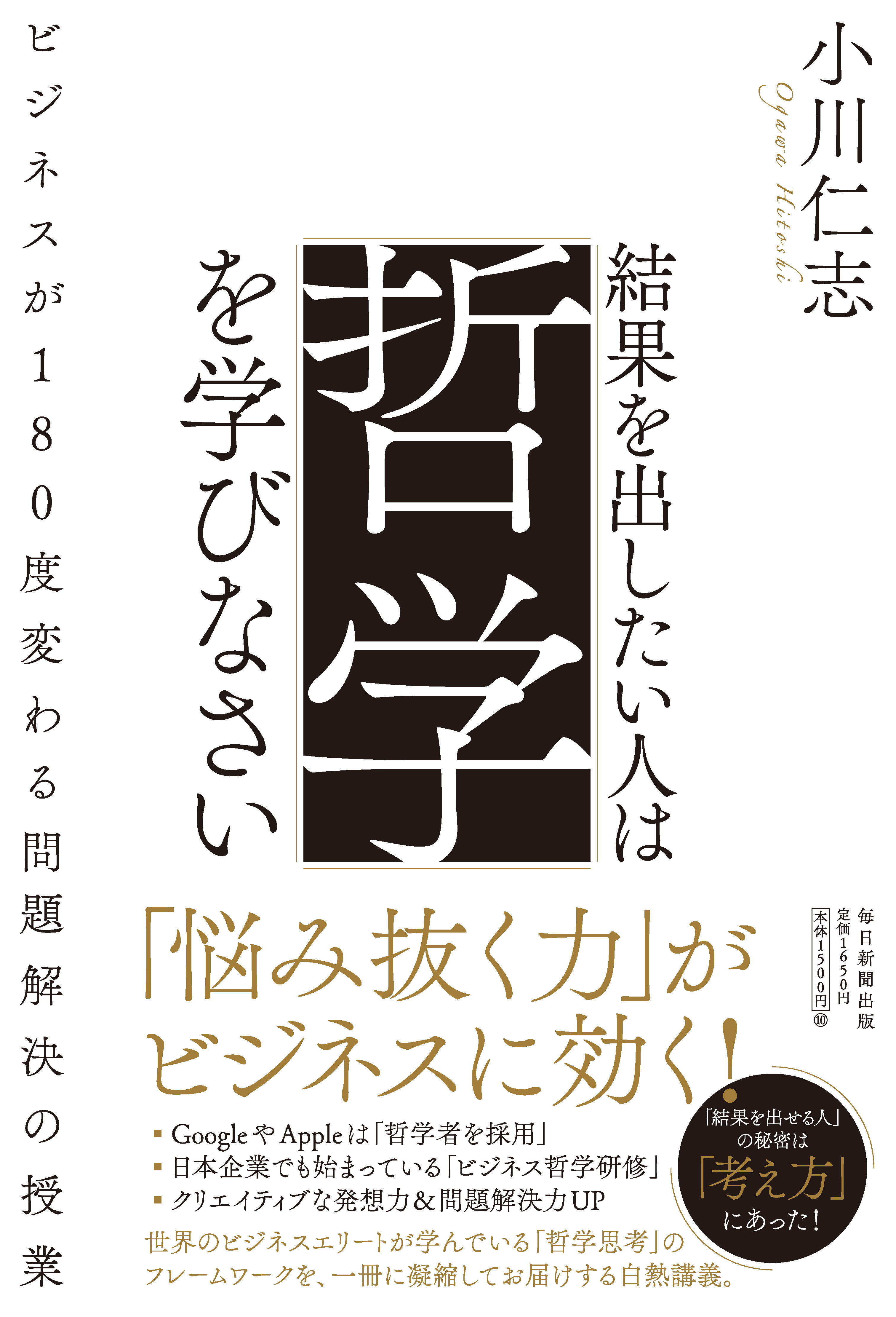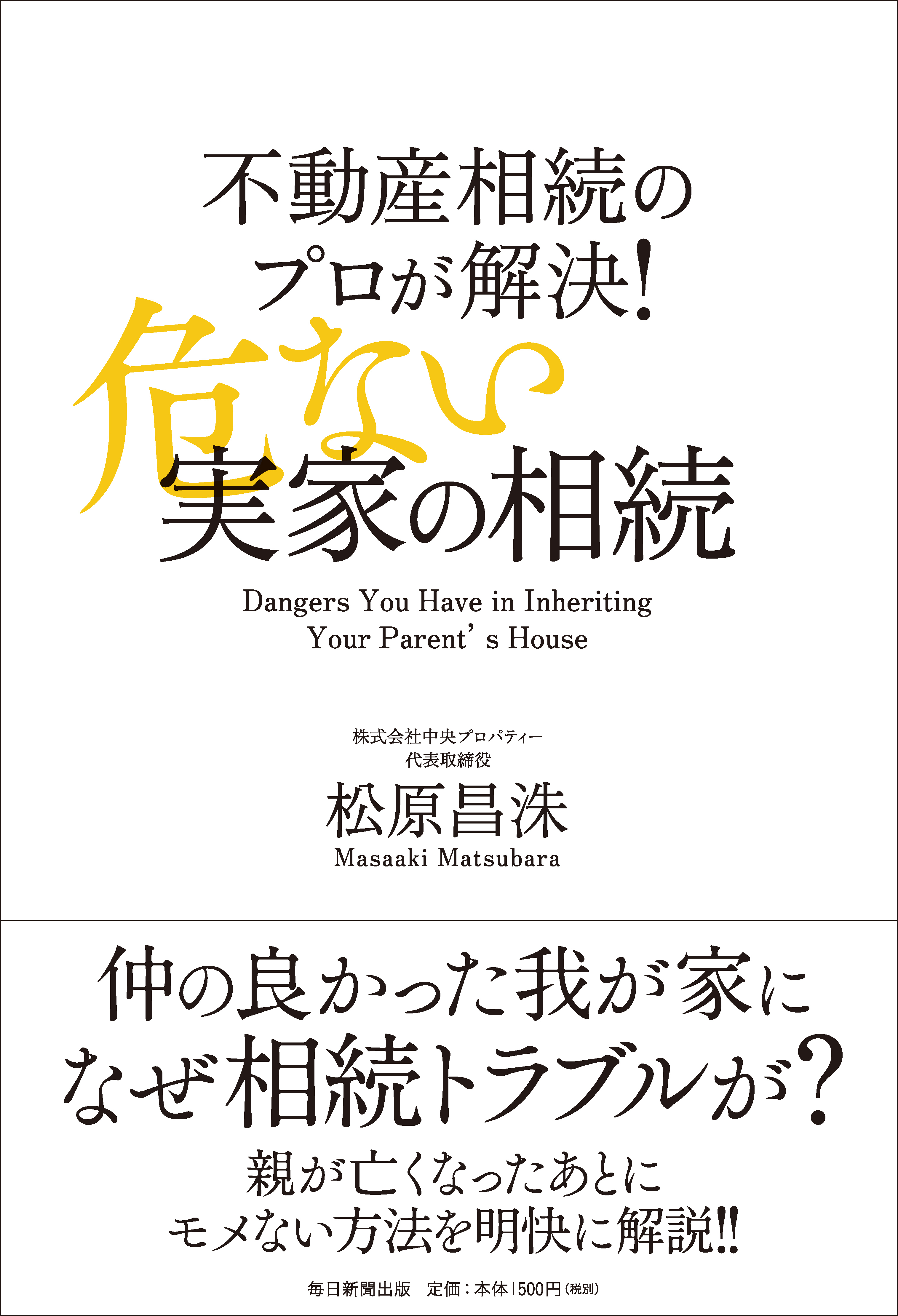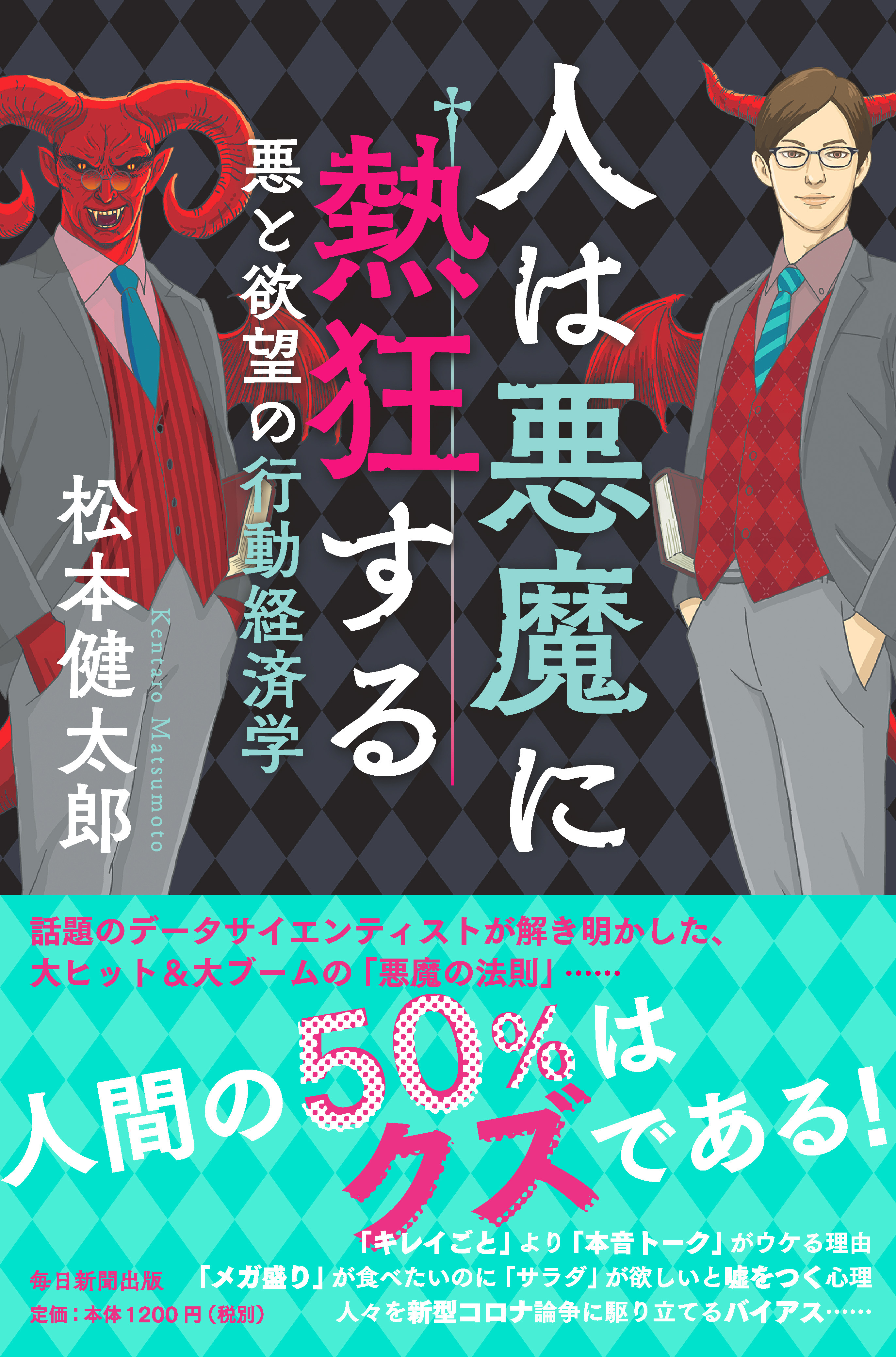アルコール燃料で、地球の未来が変わる!
なぜ、いま脱炭素社会化やカーボンニュートラルが必要なの?
石炭・石油や天然ガスの代替燃料として期待されているバイオエタノール。
エネルギー問題を解消し、環境にも優しい再生可能エネルギーの概要から現状まで、第一線の専門家が解説する。
『「アルコールで走る車が地球を救う」。本書のタイトルである。ここでいうアルコールとはエタノールのこと。では、なぜ今エタノールなのか。それは、植物由来のバイオエタノールを自動車や飛行機などの燃料として使えば、いますぐにでも二酸化炭素(以下CO2)削減の救世主になりうるからだ。この本が、読者の環境問題やエネルギーの理解の一助となれば幸いである。』──はじめにより抜粋
■目次
はじめに
第1章 エネルギーのこれまでとこれから
コラム 今こそ国産エタノール栽培を
第2章 バイオエタノール燃料
コラム トウモロコシから航空燃料を作る
第3章 エタノールで走るハイブリッド車は電気自動車に勝てるか?
コラム EVは超カッコいい! でも距離、充電に不安
第4章 「コメ」と「トウモロコシ」の潜在力
終章 私たちの意識改革と新たなライフスタイル5つの提言
■著者略歴
本間 正義(ほんま・まさよし)
1951 年生まれ。帯広畜産大学卒、東京大学修士、米国アイオワ州立大学博士(Ph.D.)。東京都立大学助手、小樽商科大学助教授・教授、成蹊大学教授、東京大学教授、西南学院大学教授を経て、2022 年よりアジア成長研究所特別教授。この間、国際食料政策研究所(IFPRI、ワシントン D.C.)、国連食糧農業機関(FAO、ローマ)、豪州国立大学(ANU、キャンベラ)で兼務。専門は農業経済学、経済発展論、国際貿易論。著書に『農業問題の政治経済学』、『現代日本農業の政策過程』、『農業問題:TPP 後、農政はこう変わる』などがある。 2010-12 年日本農業経済学会会長。東京大学名誉教授。
横山 伸也(よこやま・しんや)
1974 年、北海道大学大学院理学研究科化学専攻博士課程修了後、工業技術院公害資源研究所(資源環境技術総合研究所)に入所。2001 年、産業技術総合研究所中国センター所長。2004 年、東京大学農学生命科学研究科教授、2011 年、公立鳥取環境大学教授。東京大学名誉教授。理学博士。現在、アメリカ穀物協会顧問。専門はエネルギーシステム分析、バイオマスエネルギー変換技術。主な著書に、「バイオマスエネルギー最前線」、「バイオマスエネルギー」、「図解でわかるカーボンニュートラル燃料」など。
三石誠司(みついし・せいじ)
1960 年生まれ。東京外国語大学卒業後、JA全農入会。飼料部・総合企画部・海外現地法人筆頭副社長などを経て 2006 年から宮城大学教授。ハーバード大でMBA、筑波大で修士(法学)、神戸大で博士(経営学)取得。農林水産省食料・農業・農村政策審議会委員、財務省関税・外国為替等審議会委員、全国大学附属農場協議会副会長などを歴任。2024 年から宮城大学副学長。専門は経営戦略・アグリビジネス・食品企業経営。著書に『空飛ぶ豚と海をわたるトウモロコシ』、訳書に『ローカル・フードシステム』など。
小島 正美(こじま・まさみ)
1951 年愛知県犬山市生まれ。愛知県立大学外国語学部(英米学科)卒業後、毎日新聞社入社。
松本支局を経て東京本社生活報道部で食・健康・環境問題を担当。2018 年退職。東京理科大学非常勤講師、「食生活ジャーナリストの会」代表を歴任。食品安全情報ネットワーク共同代表。
著書は『メディア・バイアスの正体を明かす』(エネルギーフォーラム)、『フェイクを見抜く』(共著・ウエッジ)、『食の安全の落とし穴』(共著・女子栄養大学出版部)など多数。
■コラム執筆
平沢裕子(産経新聞社東京本社編集局文化部記者)
中野栄子(元日経BP社記者)